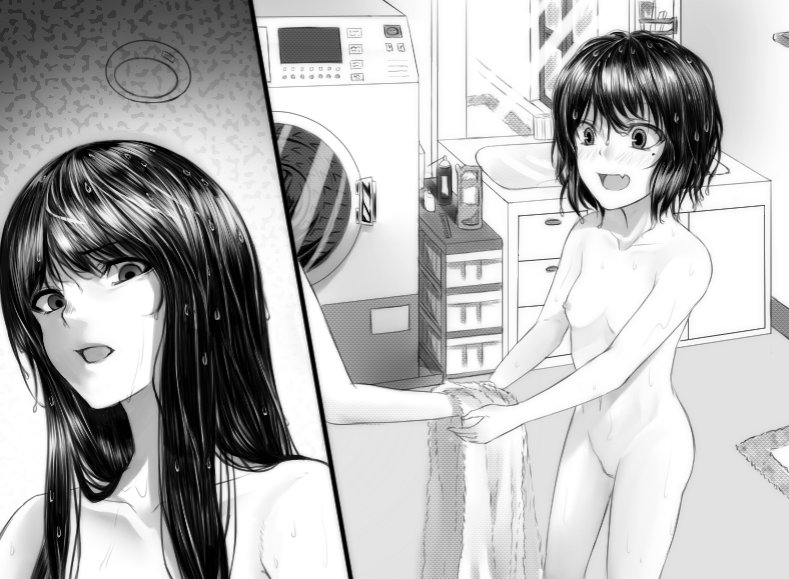【蜩】
照りつける太陽。うだるような暑さ。
むせ返るような青い草の香り。
真っ青な空に浮かぶ入道雲。
じりじりと照らされるアスファルトの中、バスから降りた一人の制服姿の少女。
黒ぶち眼鏡をかけた女の子だ。
カッターシャツは汗だくで肌着のTシャツが透け、ブラジャーの線までくっきりと浮き上がっていた。
膝を少し出したスカートから伸びる白磁の肌が美しい。
汗をたっぷりと含んだ前髪が顔に張り付き、鬱陶しそうに退ける。
どうやらバスにはエアコンがついていなかったらしい。
坂道を上り別の停留所へ向かうバスを見送れば、辺りは蝉の声以外何も聞こえなくなる。
所謂ニュータウンと呼ばれる地域、山間に作られた住宅街へ帰るため、バス停の傍にある階段を昇っていく。
コツ、コツと手すりを握りながら一段一段、踊り場が全くないここで誰か落ちないのかたまに心配になる。
やっとの思いで一番上にたどり着き、一陣の風が吹けばザワザワと木の葉が揺れる音がして、シンプルな青いカチューシャをつけた、艶やかな黒のロングヘアーが絹のカーテンのようにふわりと舞った。
思わず後ろを振り向けば、眼下に山と田んぼ、そして遠くに市街地が見える。
ジワジワと蝉時雨が降り注ぐ中、眼鏡をかけなおして彼女はまた歩を進めだした。
その背後の雑木林からの目線に気づかずに。
眼鏡のレンズのようにぐにゃりと背景が歪んで、元に戻った。
「ただいまぁ。」
「お帰り、佳那お姉ちゃん!」
春から高校生になった姉、坂口佳那は一足先に学校が始まっていた。
開いたドアの音を聞きつけた妹がドタドタと足音を立てて廊下から勢いよく姉に飛びつく。
「あー!もう、汗だくなんだからあんまり抱き着かないでよ沙希…!」
衝撃でよろめきながらも、がっしりと受け止める佳那。
頭一つ分小さい彼女をすっぽりと胸に抱きしめ、ショートヘアーのサラサラの髪を撫でてやる。
この妹は姉に頭を撫でられるのが大好きなのだ。
「えへへぇ、お姉ちゃんの匂いだぁ…」
ぐりぐりと頭をこすりつけてくる。
姉バカだと自分でも思うが、可愛らしい。
「嗅がないの!全くもー…。」
じっくり30秒ほどであろうか、姉を堪能した沙希は身体を離すと、パッと太陽のような笑みを浮かべた。
やれやれ、と言った調子で佳那はローファーを脱ぎ、パタパタと手を仰ぎながらエアコンで冷やされた室温に目を細める。
ここが天国か、と言わんが如くの表情。
「もー、なんで高校からは夏休み短くなっちゃったのかなぁ…31日まで休んでたいのに、と言うか暑すぎだよ…」
スクールバックを抱えなおし、思わず愚痴ってしまう。
ため息から外気の暑さが漏れ出て顔を顰めてしまった。
二度三度深呼吸をして、肺に溜まった熱気を入れ替える。
「大変だねぇ…お風呂沸かしておこうか?」
玄関でタオルを渡されながら、彼女は妹にお願いね、と告げる。
佳那はリビングからすぐさまキッチンに向かい、ドカッとスクールバッグを置いて冷蔵庫を開ける。
取り出したペットボトルのスポーツ飲料を、CMのようにグビッと飲み干した。
汗に濡れた髪と、細い喉が動く姿が扇情的である。
「ふー…」
ソファーに大きくもたれかかって、文明の利器の恩恵を最大限に受ける。
リモコンを手にとり、丁度自分のところに風が当たるように操作した。
目の前の机には、可愛らしい筆箱に鉛筆、そしていくつかのノートが広がっている。
適当に一つソレを手にとると、スカートの中を扇ぎ始めた。
水色のフリルのついたショーツがまぶしい。
「お母さんは?」
背もたれに身体を預けてぐいっと後ろを向く。
沙希も息抜きと言わんばかりにコップに麦茶を注いでゴクゴクと飲んでいた。
「今日は遅くなるから二人でご飯食べておいてってさー。」
そう言って手元から封筒を取り出してくる。
どうやら、そこに今日の晩御飯代が入っているようだ。
ひらりと受け取ると、かさかさと中を探って紙幣を取り出す。
「おぉー、やったぁ!5000円も入ってるじゃん!何か出前でも頼む?」
「じゃあ私ピザがいいな!」
そうしようか、と笑みを向けると、わーいと喜んで戸棚にあるデリバリーピザのチラシを引っ張ってくる。
赤を中心としたそのチラシで、大きくカーベットの上に広げて見繕っているようだ。
期間限定がいいかな、それともいつもの…サイドメニューも…等と楽しそうに選んでいる。
「あ、そうだお姉ちゃん。後で夏休みの宿題みてよ!いくつか残っていてさー。」
純真無垢な瞳を向ける沙希。
どうやら彼女は今までこの夏最大の敵と格闘していたらしい。
毎年毎年、この時期になると沙希の宿題の手伝いをするのが恒例となっていた。
そのお陰で佳那自身は先に宿題を終わらせる習慣がついたのだから皮肉なものであるが。
「しょうがないわねぇ、六年生なんだから計画くらいきっちり立てなさいよ」
山積みになったドリルを適当に開きながら応える。
どうやらこの量が多い側はきちんと終わらせているようだ。
とは言え、単純作業で出来るものばかりで自由研究とかが残っているようだが…。
「今までだったら最後まで何も手を付けてなかったから進歩してるんだよ私!」
えっへんと、最近膨らみかけてきている胸を張る沙希。
子供らしいプリントの入ったTシャツが少しだけ歪んだ。
ゆっくり立ち上がると、頭を軽く撫で、ペットボトルを潰してゴミ箱に棄てる。
「はいはい、じゃあお風呂入ったらみてあげるから、ね。」
この分ならそこまで手もかからないだろう、と勘案しつつ、バッグを持って二階の自室へと向かう。
トントントン、と小気味いい音を立てながら階段を登っていく。
西日に照らされている家は恐ろしく暑く、下手したら外よりも熱気が籠っていた。
うわ、と情けない声をあげながらKANAとプレートのついた自室のドアを開けて、いつもの位置にバッグを置く。
ムワっとした空気は湿度を良く含み、浴びるだけで汗が噴き出そうな程。
一先ず窓を開けて換気をしよう。
そう思い、カーペットが敷かれた部屋を進んで、ガラガラとサッシを開く。
山から流れる涼しい風が部屋に入りこんだ。
遠く聞こえていたジーワジーワという蝉の声がより一層大きくなる。
目の前の道路を見れば陽炎が立っていた。
そりゃ今日も暑いわ、とすぐさま戻って着替えを取ろうとする。
と、何故かベランダ部分が濡れているのに気が付いた。
室外機の排水かな?とも思ったが、二階では誰もエアコンを使っていない。
今日は雨も降っておらず、では一体何故。
首をかしげながらスリッパを履いて一歩ベランダに出ると、ニチ、と言う音がした。
びっくりして足を引っ込めると、何故か重い感触。
恐る恐る、ぐりぐりとすり潰すように足を動かすと、糊が張り付いたような感覚がする。
その液体はどうやら粘度が高いらしい。
うぇ、と気味悪そうに眉間に皺を寄せ、どうしようか思案する。
取り敢えず水で流して…と思って居ると、下を向いて無防備になっていた首の裏に水滴がボタッと落ちてきた。
ビクッと驚いて思わず上を向く。
ポタ、ベチョッ……っと怪しげな水の音が耳を打ち、つつーと人肌ほどの暖かさの液体が首筋を垂れる。
視界に入ってきたのは、透明な水まんじゅうの餡子がないタイプのような、クラゲのような、透き通っていて全体がつかめないが、天井にベタッと張り付いているのが見て取れた。
大きさは、パンパンに膨らんだゴミ袋二つ分くらいだおうか……?
あまりの衝撃に声を発することすらできない。
こんな生き物、なのだろうか、が居るなんて。
重力に耐え切れなくなったように、スローモーションで顔に飛び込んでくる。
逃げたくても足に力が入らず膝が笑って動くことが出来ない。
顔面にベドッとまとわりつき、重心を失った身体が部屋の中に押し倒される。
スリッパが脱げて飛び、体育の授業で習った受け身が咄嗟に出るも、謎の物体は自分の身体を巨大なビーズクッションのように背中に回って衝撃を吸収した。
一瞬触れた袖が濡れ、べたつき肌に張り付いてしまう。
ぶよん、と背中に押し当てられるソレ。
水分がどんどん服に染み込んで不快な気持ちになる。
だが、動く気配がない、助けてくれた、のだろうか?
「え…あ…」
困惑する佳那。
どうしよう、と迷ってしまうが、徐々に全身が沈み込んでいるため、グッと力を込めて起き上がろうとする。
「っ!?」
その瞬間、手足の部分が鉄の輪を掛けられたように固定されて、抜け出そうにも液体ごと引っ張るような形になってしまう。
更に口もガムテープを貼られたように大蛇のようなソレが巻き付いてきた
これは不味い、と思って下に居る沙希に助けを求めようと、床を叩こうともがくも、ソレがぶよぶよと緩衝材になって音を立てる事が出来ない。
どうやらこれはスライムと呼ばれる物体のようだ、昔読んだファンタジーの漫画でこんな敵が居たことが脳裏に浮かんだ。
「んー!!んー!!!」
声を出そうにも、口を押さえられて粘っこい気泡が出るのみ。
ボコッボコッと溶岩のような鈍い泡のはじける音。
両手足を拘束され、自由を奪われた佳那はパニックに陥いりかけてしまう。
ぐにゃりとスライムが蠢くと、唇がゆっくりと五本の指で撫でられる感覚がする。
まるでわいせつ行為をするオッサンのような手つき。
なすがままにされる事に恐怖に身をよじる佳那。
鼻息が荒くなり、心拍数がどんどん上がる。
一体これからどうなるのか、頭が真っ白になっていく。
さわ、さわとスライムに浸かっている背中や、二の腕が触られ始めた。
ブラの感触を確かめられ、半袖のカッターから出るほっそりとした腕をむにむにと揉まれる。
ねっとりと、しゃぶりつくすように。
ぞわぞわっと寒気が広がった。
唇の中で歯がガタガタと震えだす。
長い髪の毛がゆっくりとスライムの中でゆらめいた。
梳くように頭皮にまで入りこみ、優しくなでられる。
グチュグチュとカチューシャの間にも押し込まれるように入った。
一つ一つ手が増えていき、まるで胴上げをされながら触られているかのよう。
スカートの上から尻を触られ、太もものハリを確かめられる。
イヤイヤと首を振ろうとするが、それすらも抑え込まれた。
ごつくて太い透明な指が、彼女の口の中に入りこもうとしてくる。
口を紡ぎ抵抗する佳那。
嫌いなものを無理やり食べさせるような動き。
全身が硬直し、手をギュッと握りしめる。
ふーっふーっ、とカラダに酸素を取り込もうとする鼻が、グッと抑え込まれた。
「ふごっ!」
小さい鼻の中に、ぐいぐいと入りこんでいくスライム。
力ずくで下から押し上げられたお陰で、彼女の鼻は子豚のように歪んでいく。
酸素の供給元を断たれた佳那は残った肺の空気で押し返そうと試みるが、全く足りない。
寧ろ、もっと空気をよこせと叫ぶカラダの動きに抗えず、鼻をすすってしまう。
風邪を引いた時に鼻が詰まった時の感覚。
寝ているときに窒息しそうになった夢を思い出した。
スライムはその姿が面白かったのか、二度三度と鼻フックを繰り返した。
余りの苦しさに、じわっと涙が漏れた。
全身から力が抜けて行く。
握りしめていた手が開かれ、スライムの手が内股に滑り込んだ。
ショワワッと小水が彼女の水色のショーツを濡らし、スライムに染み込んでいく。
少し黄色い液体がスライムの中に漂うが、すぐさま分解され、消えてなくなった。
グイッと足を開かされて湯気の出そうな程暖かいショーツが蝕指に撫でられる。
ゾクッと背筋を震わせ、じゅぷじゅぷと沈められていく。
紡がれていた口に隙間が出来てその中へスライムの指が入りこみ始めた。
「がぼっ…」
入りこみやすいように、鼻に入っているソレが脈動し、喉とのつながりの部分にフックのようにひっかけ、顔を上に向ける。
額の部分までスライムに浸かり、眼鏡が少しずれた。
スライムは彼女の小さな口を目いっぱいひろげ、満たすように中へ入りこんでいく。
桜色の唇を這うように口内へ侵入していくスライム。
唇の裏、歯茎、几帳面な彼女がしっかり毎日磨いている白い歯、その隙間、今日食べたモノの食べかすをも呑みこんでゆっくりと、しかし押し寄せる濁流のように入りこんでいく。
人肌ほどの生暖かいソレが不快感を加速させた。
歯肉を浸食し、舌の裏、からゆっくりと包み込み、スライムで満たしていく。
その圧力に顎が外れ、口内が更に広くなる。
舌がだらんと浮かんでいるのが見て取れた。
扁桃腺を越え、野球ボールほどの質量だろうか、それほどのスライムが彼女の口の中に納まった。
そして、鼻から侵入したスライムと合流する。
透明なソレにより、彼女の綺麗なピンク色の口内が丸わかりだ。
そのまま、ゴポッゴポッと汚い音を立てながら喉の奥へと侵入を始める。
先ほどスポーツドリンクを飲んでいた同じ道を追いかけるように。
上を向かされた彼女は口から胃の奥まで一直線。
粘度の高いスライムは水のようにポタポタ落ちるのではなく、大きな塊となって、ボトリと流れ込んでいく。
拘束されていない彼女の細い喉が嘘のように大きく膨らみ、首の骨を軋ませながら中へ中へと落ちて行く。
ギチギチと軋むように脈動し、たっぷり5秒ほど時間をかけ嚥下させられる。
食道部分も広げられ、胸がぐぐっと膨らむ。
肩甲骨が背中側により、反って胸を張った状態になったのだ。
それが収まると、ぎゅるる、と異物に胃が反応して、佳那の腹がググッと萎み、そして膨らんだ。
その間に、股からもスライムが侵入しようとしていた。
ショーツをゆっくりとずらし、彼女の菊穴へと。
皺をなぞるように、ゆっくりとねじ込まれて行く。
ゴポッと喉が脈動して気泡が漏れた。
完全に意識を失っているが、佳那の身体は本能で抵抗するようにビク、ビクと痙攣する。

「ぼ…ぼ…」
スライムが大きく力を籠め脈動し、中に入りこむたびに痙攣。
また、脈動して痙攣。
まるで二つの全く違う生き物が、一つになったかのように。
腹がポッコリと膨らみ、腸の形が浮き上がる。
内臓の空気が押し出されて、気泡が更に噴き出てきた。
このまま茹でればスライムのソーセージでも完成するか、と言うような状態。
ミヂミヂと襞の一つ一つまで広げ、押し込まれて行く。
身体が自動的に受け入れ、楽な姿勢をとれるように反り始めた。
あまりの肉体への負担に、自動的に受け入れる姿勢になりつつ佳那のカラダ。
実験台に載せられるカエルのように無様な姿である。
更に、彼女の髪に隠れた耳をかき分けるように蝕指を伸ばし、ジュルジュルと入っていく。
佳那には抵抗する力など残されていなかった。
食道や腸内は、便宜上人体の外側に位置する場所。
だが耳の中から先は、モノが入ってはいけない内側。
ぐり、ぐりと大きくうねる度に口がパクパクと動き苦悶を訴える。
少し動けば、それに連動するように両目がぐいっと動いた。
酸欠状態になったカラダは首や額に青筋が浮いている。
顔色が青紫にも差し掛かろうとしていた。
痙攣も力がなくなり、痺れるようにプルプルと動いているのみ。
整った顔は完全に崩れて酷い有様になっている。
スライムは徐々に体積を減らし、佳那を床に仰向けで寝かせてナメクジがのしかかるような姿勢へと変化していった。
首を項垂れ上を向かされていた顔が天井へ向きを変える。
ぐぐっと腰をかがめさせると、むっちりとした尻を突き出させて穴をなるべく上に持って来るようにさせた。
その間にもピクンピクンと彼女の痙攣は続いている。
そして、ズチッと蠢くと、水の張った洗面台から排水するように、二つの入口へ渦が発生した。
内圧が更に増して佳那の眉間に皺が寄る。
ゴボボ、ガボボと気泡が大量に発生して、水あめのように空気の線が描かれて行く。
風船が萎むようにどんどん質量が減っていくが、その度に彼女は釣り上げられた魚の如き痙攣を起こす。
ガクッビクッと両手足を震わせ、体内に残った空気をブヂュッと放出した。
「がっ…ご…ぉ…」
体積はぐんぐん減り、ついに彼女の顔が解放された。
あれだけベドベドになっていた服や髪の毛が乾燥機にかけられたように乾いていく。
全てがスライムになり、佳那の中に入っていったのだ。
口から異音を発しながらもだえ苦しんでいる。
白目を剥いて震え、その痙攣は波が引くように徐々に小さくなっていった。
「ごぽっ…ひゅーっ、ひゅーっ」
永遠のようで一瞬のような、出来事。
彼女のカラダは久しぶりの酸素に歓喜し、浅く呼吸する。
その間にも、ゴポッゴポッと水が沸騰するような音が全身から漏れ出ていた。
巨大なスライムが中に居るにも関わらず、彼女のカラダの外見の変化は一切ない。
それから少し経った頃であろうか、下から沙希の声がした。
「佳那お姉ちゃん!お風呂沸いたよー!」
その声を聞いた途端、ピクッと人差し指が動き、目に生気が戻ってくる。
すぅ、と息を吸い声を張り上げた。
「沙希ごめん!ちょっと今電話してるからもう少し後にするねー!」
わかったー!と元気な返事が返ってくる。
その口調は妹が聞いても全く違和感を感じないモノであった。
改めて仰向けのまま、深く息を吸い、そして吐く。
もう一度呼吸をしようとしたとき、膨れ上がった胃が蠢いた。
「げぇぇ…っぷぅ…」
機械が熱を排出するかのような長いゲップ。
普段の彼女であれば絶対にしないような下品なモノ。
ゆっくりゆっくりと両手を天井にかざし、細く長い手を閉じたり開いたりする。
と、視界がぼやけている事に気付き、眼鏡をかけなおした。
ギシギシと軋むカラダを無視しながら、上体を起こしてもう一度深呼吸。
グッと俯いた時に背中にひっかかるブラの感触が心地いい。
勢い余って眼鏡が落ちないように気を付けながら、ギュッと自分を抱きしめた。
「はぁぁ…」
熱い湿り気の帯びた息を長く吐いて恍惚に浸る。
ニヤリと下卑た笑みを浮かべる佳那。
そう、彼女はもう既に彼女であって、彼女ではないのだ。
「ふふっ…女の子の部屋の匂いだぁ…凄いなぁ、私の部屋なのにこんなに興奮してる…あ、勿体ないから窓閉めちゃお…」
蕩けるような甘い声。
口調はそのままなのに、中身が違うだけで雰囲気がガラッと変わる。
窓とピンク色のカーテンを閉めると、薄暗い女の子の部屋が広がった。
ベッドに置かれたぬいぐるみの数々も、勉強机に置かれている教科書も、戸棚の小物や少女漫画の単行本も、クローゼットにどんな服が入っていてどこに下着があってというのも、全て手にとるように分か
る。
分かるのに、あまりにも新鮮。
鼓動が早まる心臓を押さえるようにもう一度、佳那の部屋の香りを肺一杯に取り込んだ。
「すぅ~っ…はぁ~……」
ニタニタと笑いながら、彼女はドサッとベッドに倒れ込む。
女の子特有のいい香りが幾重にも折り重なって鼻腔を揺らした。
落ち着いたはずなのに、呼吸がまた荒ぶりはじめる。
口の中が涎を分泌してごくりと喉を鳴らした。
男の思考が混じる嫌悪感からか、背中がぞわっとする。
思わず笑みが零れるが、ピクッと抵抗するように頬が震えて涙が零れた。
眼鏡を外し、涎が垂れている唇を拭う。
カラダを無理やり起こして、正面にある姿見の方を向いた。
涙かそれとも視力か、ぼやける視界。
ゆらりと立ち上がると、勉強机に置いてあるインスタントのコンタクトレンズを手にとった。
目に何かを入れるのが怖くて勇気が出なかったソレ。
躊躇いもなく佳那は一つ取り出すと上を向き、初めてとは思えないスムーズさで両目にはめ込む。
そしてもう一度姿見の前に立った。
「やっぱり私、こっちの方が可愛いわね。ダサい黒ぶち眼鏡もいいけど…♪」
何よりも耳にかかる感触が鬱陶しくなくていい。
頭を振ればCMのようにさらりと髪の毛が舞う。
一房握って顔の前にやれば、いつも使っているトリートメントの香りが漂ってきた。
すんすんと鼻を鳴らして確認し、じゅるりと口に含む。
「はむっ…じゅるっ…んっ…おいひ…」
実際には鉄のようなよくわからない味しかしないのだが。
それでも、佳那にとっては甘美に思えた。
自分を支配していると実感できるのだ。
ハーモニカを吹くように髪の毛の束の途中をしゃぶる。
細く柔らかい毛に舌を当てて食いこませれば、男との違いに驚愕してしまう。
「ふはっ…凄くエロいわね……普通の女の子は自分の髪の毛なんて食べないよ……でも私はもう普通じゃないもんね♪」
流れるようにカチューシャを外してもう一度首を振る。
外したソレは、濃い汗とシャンプーの混じった匂いがして、思わず咥えてしまった。
コリコリとしたプラスチック、柔らかい外周の布部分の触感が心地いい。
ほんのり甘くしょっぱいそれ、こんなところにまで雌の味があるのかと感嘆してしまう。
またヒクヒクと目尻が痙攣した。
彼女の精神が抵抗しているのだろう。
ニコッと笑ってベドベドになった髪の毛を放置しながら、プチプチとカッターシャツのボタンを外していく。
そのまま脱ぎ捨て、シャツも脱げばショーツとお揃いの水色のブラジャーが露わになった。
ティーンズ向けのソレもためらいなく脱ぎ、プルンとした張りのある胸が現れる。
既にカラダは出来上がっているのか、桜色の乳首はピンと立っていた。
適当にセクシーポーズをとりながら考える。
手を頭の上にやって腋を見せれば、汗で少々ベタついたそこが露わになった。
丁寧に処理されているらしいそこ。
犬のように匂いを嗅げば濃厚な汗のにおいが鼻を刺激した。
そして胸を揉もうとすれば細い指が乳房に沈みこむ。
「えーっと、84、56、82のDカップか…これでもまだ成長途中なのよねぇ…このブラお気に入りだったのに、すぐ入らなくなりそうで嫌になっちゃう。でも、これからはいっぱい揉まれてもっと大きくなる
から気にしてちゃダメよね!」
一切垂れないそこが粘土細工のように形を変えた。
柔らかく暖かい感触、ピリッとする快楽、そして速度を上げる心拍が手に伝わってくる。
たった10分前までは見向きもしなかったソレに夢中になる佳那。
童貞のように鼻の下を伸ばしながら、姿見の前で痴態を晒す。
むにむに、ふにふにと美少女が胸を揉む姿はまさに至高のオカズだ。
「んっ…こうやって下から持ち上げて…んぁ…記憶を辿るよりやっぱり実際にやった方が気持ちいい…」
トロリ、と太ももを伝う液体の感覚。
濡れているのだ。
腰の部分のチャックを外してスカートを脱ぎ、М字開脚の姿勢になる。
「あれ…ちょっと高さが足りない…」
床に座った状態だと股間部分が映らない事に気付いた佳那はそそくさと姿見をベッドの手前に移動させる。
ショーツ一枚でやっている姿はある意味間抜けのようにすら見えた。
改めてベッドの上でM字開脚すると、そこには花園が広がっていた。
薄い陰毛が愛液で張り付き、上から透けて見える。
ツンとした雌の匂いが立ち上った。
ゆっくりと、クロッチ部分を上からなぞる。
「んひっ…」
ぞわぞわっとした感触。
だが不快ではない、良く知ったモノ。
ゆっくりと下からなぞり、少し膨らんだところをキュッとつまめばヒクッと全身が震えた。
「これが私のクリトリス…」
にへへ、と唇が釣り上がる。
両手を腰に沿えて、ゆっくりと下着を降ろしていく。
ヌチッという音がしてクロッチ部分に糸が引かれ、陰毛の束が持っていかれそうになる。
まるでAV女優のようにねっとりと目線を姿見に寄せて、右足、左足と脱いでいった。
ホカホカのソレを裏返すと、赤い部分が尽きかけたスイカのようにクロッチ部分へ吸い付く。
ジュルッジュルルルと下品な音を立てながら、舐め、抜けた陰毛を食べる。
ねっとりとして酸っぱい、だが頭がくらくらするほど美味しい。
ぷはっと口を離せば、ショーツは唾液まみれになり口元には愛液がべっとりとついていた。
だが、何か物足りない気持ちになってくる。
ふっと思い立って立ち上がると、一直線にクローゼットにむかった。
上から三段目の一番左の棚を引けば、そこには賽の目に画用紙で区切られたショーツたちとブラジャーが。
迷わず、落ち着いた藍色のショーツを取り出す。
それはサニタリーショーツであった。
広げ、ひっくり返せばクロッチ部分には赤い染みがついている。
経血である。
佳那は迷わずそれにむしゃぶりついた。
洗剤の味の中に、ほんのりとレバーのような血の香りがする。
「んっ…ふっ…じゅる…っぱ」
思わずほっそりしたお腹を撫でた。
ここから排泄されたモノが、ここについているのだ。
女の子なら少し気にするか気にも留めないモノにとても興奮させられている。
このカラダを使っているという事に、とてもとても気分が良くなった。
再び姿見の前に戻って、自慰行為を再開する。
クパッと秘部を開けばサーモンピンクの穢れを知らないおまんこが露わになった。
奥からトプッと愛液が漏れ出してくる。
先ほどの間にも更にこのカラダは興奮していたようだ。
「んっ…」
つぷっ、と右手の人差し指と中指を突っ込んだ。
別の生き物のように脈動するそこは、とても熱く茹っている。
それと同時に、異物感と快楽の信号が脳へ送られてきた。
クチ、クチと指の腹でざらざらした部分をなぞっていく。
「んぁっ…」
咥えていたショーツに力が籠った。
ずくん、と腹の奥底が震える。
頭がぞわぞわして、視界がブレた。
ゆっくりと息を吐いていくと、ドクン!と心臓が大きく跳ねた。
「ん゛っ!」
くぐもった声が漏れ出す。
歯を食いしばって、秘所に突っ込んだ指に力が入った。
ギシリとベッドが軋む。
「あ゛っ…あぁっ!」
記憶が流れ込んでくる。
今まで生きてきた記憶、16年間の全てが。
それはスライム…『彼』にとってはオカズの宝庫。
今まで見てきた女性の裸や自分自身の成長、友人たちとのエッチな思い出。
AVなどでは見られない生々しいそれらは強烈な快感を産みだす。
入っている精神の昂りにカラダは生々しく反応し、子宮が疼き、愛液が漏れ出した。
「はぁっ…んぁっ…」
ピクッピクッと震えては熱い吐息を吐いた。
『坂口佳那』の記憶が全て閲覧され、取り込まれて行く。
そして、その一つ一つに、男の欲望が塗りたくられる。
彼女が、彼女でなくなっていく。
石臼で挽かれるように、ゴリゴリと。
「んっ!」
ズクンと子宮が声を挙げた。
孕みたい、いや、孕ませたいと。
無いはずの相棒があるようにすら錯覚させられていく。
そして最後に現れた大切な記憶。
妹の沙希の記憶だ。
小さい時から可愛がってきた彼女…
きっと私に似て美人に成長するんだろうなぁと。
ズキンと頭が痛んだ。
「そっかぁ…『これ』が私の一番大事な記憶…なら、滅茶苦茶にしないとね?」
思春期の女の子の精神など容易い、土台を崩してしまえば後はズブズブだ。
このカラダを染め上げる事が出来ると思えばどんどん興奮してくる。
残った佳那の理性がせき止めようと、背筋を震わせるがそれすらもスパイス。
あの薄い唇にキスをしたい、発達途中の胸にしゃぶりつきたい、初潮が来たばかりのおまんこを滅茶苦茶に舐めたい、沙希を食べたい、私のモノに、塗りつぶしたい…!
「あ゛っ…あ゛っ…あ゛あ゛あ゛!!!」
やめて!と言わんばかりに眉間に皺が寄った。
ヒクヒクとカラダが悲鳴を挙げる。
それでも彼女は止めなかった、記憶の中から沙希を引っ張り出しオカズにしていく。
しゃぶりつくこのショーツが妹のモノだったらどれほどいいことか。
黒い願望が佳那の頭を埋め尽くしていく。
「ん゛ん゛ーーーーー!!!!」
洗濯物の際によく見るソレを思い浮かべながら腰をくねらせた。
スライムのようなねっとりした液体が股間を濡らす。
絶頂したのだ。
ガクビクッと全身を痙攣させながらきつく締めあげる膣の感触を味わう。
ドサッと仰向けに倒れ、天井を見上げた。
遠くに蝉の声が聞こえる部屋に、荒い息だけが響く。
「ふひっ…ふふっ…沙希ぃ…」
瞼を開ければ、涙が零れ落ちた。
瞳孔が開ききった瞳でそれを一瞥し、手の平で掬ったそれを握りつぶす。
その姿は悪意に満ちていた。
「お姉ちゃん、遅かったね。」
お風呂が沸いてから30分程したほどだろうか。
ようやく佳那が降りてきた。。
沙希は未だに夏休みの宿題と格闘しているようだった。
「ちょっと電話が長引いちゃってさ…そうだ沙希、一緒にお風呂に入らない?」
汗だくになっている彼女はそんな提案をしてくる。
小学校低学年くらいまでは一緒に入っていたが、その後はめっきり入らなくなった。
家族旅行で風呂に入った時くらいだろうか。
まぁ、せっかくだしと沙希は自分を納得させた。
「ん、わかったー。ちょっと待っててね!」
トタトタと階段を駆け上がっていく沙希。
奥側にある自分の部屋へ向かう時、何かの違和感に気付いた。
何と言うか、むせ返るようなよくわからない匂いがする。
「…?」
知識の無い彼女に一体何が起きているのかなど察知することは出来なかった。
だが、明確に引っ掛かりを覚える事になる。
適当に水色のキャミソールと黄色のショーツ、そしてゆったりした上下の部屋着を回収して風呂場へと向かった。
違和感は続く。
脱衣所で脱いでいる時も姉はチラチラとこちらの方を伺ってくるし、自分の身体を見て変な声を挙げている。
何と言うか、クラスの男子みたいな不愉快な視線。
一体どうしてしまったというのだろうか。
「どうしたの?」
何でもないように小首を傾げて問いかけてくる佳那。
それは沙希のよく知っている姉そのものだ。
もしかしたらずっと宿題をやっていたから疲れているのかもしれない。
そう自分を納得させて、一緒に浴室へ入っていく。
キュッとシャワーを捻ってお湯を出した。
少し冷たい水だったモノがどんどん温かくなっていく。
「じゃぁ、洗いっこしようか。」
先に洗う?と目で問いかけてくる佳那。
だがなんというか、今身体を預けるとまずいんじゃないかと言う考えが沙希の頭をよぎった。
「お姉ちゃん汗かいてるでしょ、先洗ってあげるよ!」
そう、ありがとう、と言って佳那はバスチェアに座った。
昔はよくこうやって二人で洗ったり洗われたりしたものだ。
「じゃ、頭流すよー」
シャワーを手にとり、佳那の長い黒髪に水分を含ませていく。
憧れの姉のソレは汗が随分溜まっているらしく、少しベタついていた。
美容師さんみたいな真似でシャワーを押し当てたりしながら洗っていく。
そして、シャンプーを手にとって頭皮を優しくマッサージした。
子供らしい少し丸い指の先が佳那の頭を刺激する。
「かゆくない?」
「ん、気持ちいいよ。」
良かった、と内心安心しながら、再び洗う事に専念する。
クラスの女の子と、髪は女の命!って言われていたからかなり気を使っていた。
まんべんなく泡立ち全面が洗えたら次はシャワーで流していく。
長くて量が多いため、どうしても手間がかかるが仕方ない。
沙希はこういうのが苦手なためショートヘアーだった。
故に、尊敬と憧れと言うモノは常に持っていたのである。
ゆったりと洗い流せば、次はトリートメントだ。
先ほどのシャンプーとは違って髪の毛全体に満遍なくかけていく。
根元から毛の先まで、余すところなく。
小さい手で何度も梳きながら。
「あはは、私より丁寧だね、沙希。」
「そう?やっぱりお姉ちゃんの髪は綺麗だからさ、力入っちゃうよね!」
目を閉じながら笑みを浮かべる佳那。
思わず沙希も笑ってしまう。
でも手の集中力は逃さずに。
「沙希も後で同じ事してあげよっか?」
「えー、私はシャンプーだけでいいよぉ」
「まぁまぁ、そう言わずに。」
そんな雑談をしながら、しっかりとトリートメントをかけた沙希は姉の頭を濯いでいく。
大事なのは髪の毛に残らないようにする事。
濯ぎ残しがあればそれだけダメージに繋がってしまうからだ。
シャンプー以上に丁寧に丁寧にシャワーをかけていく。
全て流し終えたら、次はタオルで丁寧に巻いていった。
身体を洗う際に邪魔にならないようにする為である。
スポンジを取ると、ボディーソープを付けて泡をたてていく。
「強くない?」
「ん、だいじょうぶ」
髪の毛を洗うのと同様に背中を優しくこすっていく。
白磁の肌が泡に包まれてまぶしい。
その後は腕、手の先、腋や脇腹を丁寧に丁寧に。
足やお尻もである。
すらりとした肉付きのいいカラダは、沙希に大人の女性を彷彿させた。
「前はどうする?」
「じゃあ前も洗ってくれる?」
そう言われて、お腹の部分や鎖骨の部分、内腿も洗っていく。
流石に後ろからは厳しいので、前へと移動した。
胸は素手で…だが何と言うか、ドキドキしてしまう。
「んっ…」
聞いたことの無いような姉の声がした。
下乳を洗い、乳房に泡をつけていく。
乳輪が広がって乳首が隆起していた。
沙希は、そんな現象をしらない。
気にはしつつも、優しく洗っていく。
コリッとした感触がして佳那がまた悩ましい声を挙げた。
思わず意識し始めてしまうが、なるべく気にしないようにする。
次に股間部分。
ムワッとした匂い、沙希はその香りに覚えがあった。
先ほど姉の部屋から漂っていたモノに似ている。
「お姉ちゃん、これどうしたの…?」
「あぁ、ちょっとね…ごめん、洗ってくれる?」
そう指示される。
知識の無い沙希にはどういう現象なのかさっぱりだ。
言われるがままに、彼女は恐る恐る指で触れた。
クチッと粘度の高い液体が絡まっていく。
「んっ…」
また艶めいた声が。
本当に大丈夫なのか、と思いつつ洗っていく。
だが、とめどなく溢れる液体にじれったくなった。
「これ大丈夫なの…?」
「ごめん、ナカが汚れてるからそうなっちゃってるみたいで…ナカもお願いできる?」
自分でも洗ったことの無い部分。
大人は大変なのかもしれない、と無理やり納得させる。
人差し指をクチッと差し込んでいく。
そうすれば、またドロッと液体が零れてきた。
ひく、ひくと指が締め付けられる。
チラッと顔を向ければ、もっとして、と目で促された。
指をもう一本入れて奥へ奥へと進んでいく。
そして動かしてみたら、佳那の身体が跳ねる。
痛かったのかなって思ったけどもどうやら違うらしい。
これでいいのかな…と考えながら動かしていたら、バッと抱きしめられた。
泡だらけの素肌がぬめって変な感じだ。
「お姉ちゃん…?」
「ごめん、沙希…人にやってもらうの初めてで、ちょっと、ね。もっとして?」
「う、うん…」
はぁはぁと熱い吐息が耳を打つ。
沙希はまた指の動きを再開した。
その度に、キュッ、キュッと中が締め付けてくる。
何と言うか不思議な気分だ。
いけないことをしているような、ちょっとクラクラしてくる。
「んっ…沙希…もっと…」
いつもより高く甘い声にどぎまぎする沙希。
それでも姉の言う事を守ろうと、続けて行く。
佳那のカラダがピク、ピクと不規則に痙攣している。
締め付けも、抱きしめる力もどんどん強くなっていった。
指の感触がどんどん遠くなっていく感じがする。
ずっと圧迫され続けているからだろうか。
「っ…はぁ…んっ…」
沙希の心拍数もどんどん上がってきた。
知識になくても、本能でそうなっているのかもしれない。
初潮を済ませたお腹の奥底がズクンと揺らいだ。
「っっ――!!」
ビクッガクッ!と大きく震える佳那。
びっくりして沙希は指を抜いてしまう。
絶頂してしまったらしい。
くたっともたれかかってくると、そのまま押し倒されてしまった。
シャワーが二人の身体に降り注ぐ。
「大丈夫?おねえちゃ…」
「沙希ぃ…」
目を合わせた沙希は、蛇に睨まれた蛙のように動けなくなってしまった。
瞳孔が開いた目、明らかに正気ではない。
薄くピンク色に染まった肌が扇情的…だが。
口からはボソボソと沙希、沙希と何度も呟いている。
「おねえ、ちゃん…?」
瞼をヒクヒクさせながら床に手を当てて逃げ出さないように抑える佳那。
そのカラダからは、排水溝のような鈍い水の音が聞こえる。
背筋が凍りついた。
今、目の前に居るのは本当に姉なのか…?
「さ…きぃぃぃぃ!!ごぼぼぼっぼぼぼ!」
ぐりん!と白目を剥いて佳那の口から大量のスライムが噴き出してくる。
消防車の放水のようなそれは瞬く間に沙希のカラダに絡みついて拘束していった。
悲鳴を上げる間も無い一瞬。
鼻からもドバドバとスライムを吐き出し続けた佳那、なんと10秒ほどで全てを出し終わってしまった。
「げぇっ!げほっ!…ごほっ…わた…し…なんで、さきにこんなこ…うぉぇぇっ!!!」

スライムが侵入してからさっきまでの事を覚えている様子の佳那。
だが、普段の自分なら嫌悪するような行動に思わず嘔吐してしまう。
胃の中には何も無いから出るはずもないのに、何度も、何度も。
目の前ではスライムに覆われた沙希が苦しみながら乗っ取られようとしていた。
ガタガタと震えるカラダに鞭打って何とか助けようと試みる佳那だったが、うまくいかない。
それよりも、内に秘める感情に困惑していた。
苦しんで乗っ取られて行く沙希に、興奮していたのだ。
ソレをまた頭を振って否定する佳那。
おかしい、これはおかしいと。
また嘔吐してしまい、ベタベタと唾液が浴室の床に垂れる。
沙希の方は、まるで映像を早回ししているような動きで抵抗しながらスライムが中に入りこんでいっている。
口、耳、尻の穴から。
既に白目を剥いており気泡がゴボゴボとスライムの中を舞っていた。
とろり、と佳那の秘部から愛液が漏れる。
―――愛しの沙希が、乗っ取られて行ってる…私と同じように…染め上げられ……
「違うっ!」
声を荒げて否定した。
その感情は私のモノではない、と。
だがそうしている暇は佳那にはなかった。
気づけば、沙希のカラダの中にすべてのスライムが入りこんでしまったのだ。
「さ、沙希!」
「ん゛っ!…ん゛ん゛ん゛ん゛ん゛!!!!」
仰向けに倒れる彼女の肩を揺さぶると、全身を嘘のように震わせながら絶頂した。
きっと沙希も初めて出すような艶めかしい声。
思わずドキリとしてしまう。
自分と同じようにうっすらとピンク色になった肌を眺めて唾液が分泌された。
再び首を振って考えを改める。
「ふふっ…どうしたの?おねえちゃん…」
目を開いた沙希の瞳孔は、カッと見開いていた。
唇が釣り上がり、ニタリと嗤う。
その表情に見覚えがあった。
私がさっき、姿見の前でやっていた…
「貴女、一体誰なの…!?」
ガッと肩を掴んで揺さぶる。
きっとあのスライムだ、アレが何かをしているに違いない。
「い、痛いよお姉ちゃん…」
目尻に涙を貯めて訴える沙希。
それは私が良く知っている彼女で…
でも、それも演技…演技じゃない…?
頭が混乱してくる。
「だ、騙されないわよ…!私が沙希に変な事したのも貴女のせいでしょ!」
声を荒げてぴしゃりと言う。
それはある意味、願望でもあった。
これは私ではない、と否定したかったのだ。
「ふふ…じゃあ説明してあげるから、どいて?」
「そんな事出来る訳ないじゃない!早く沙希から出て行って!」
ニヤニヤと嗤う沙希に叫ぶ佳那。
だが、彼女は全く動じない。
支配者はこちらだ、と言わんばかりに。
「えぇ…?いいのぉ、今の私なら、舌を噛み切ったりとかしても全く痛くないんだけどなぁ…その時にはお姉ちゃんに乗り移ればいいし?」
「ッ!!」
身体が固まった。
生殺与奪の権利は相手にあるという事を思い知らされたのだ。
コイツに滅茶苦茶にされるかもしれない。
それに妹が居なくなれば、自分は耐え切れないだろう。
「どう、すればいいの…」
「取り敢えずお風呂、上がろっか。のぼせちゃうからね!」
降り注ぐシャワーで二人のカラダは十分に洗い流されていた。
無言でバスタオルを渡す佳那。
それに笑顔で沙希はありがとう、なんて言ってのける。
不愉快そうに眉間に皺を寄せた。
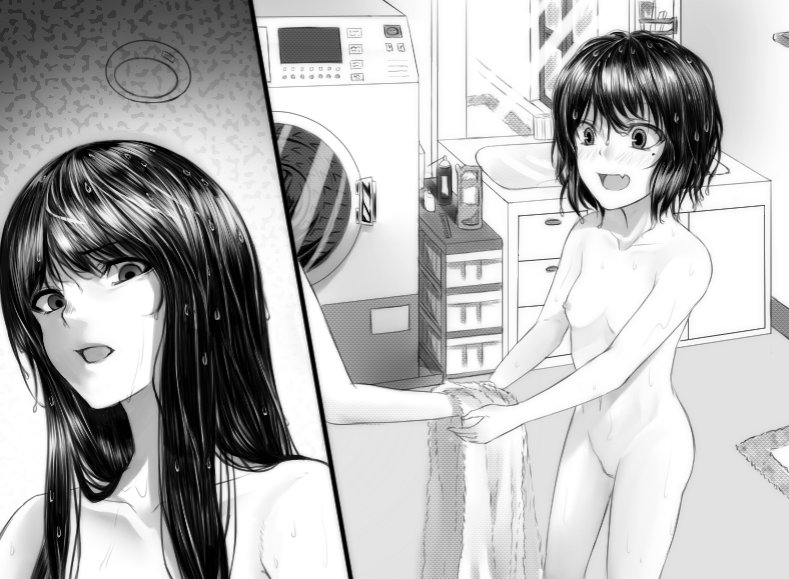
「沙希の真似をしないで…」
「えー、お姉ちゃんまだ立場分かってないの?」
「ッ…!」
ドライヤーを当てながらまた全身を震わせる佳那。
頭の中は混乱しぐるぐると回っていた。
「じゃあ罰として、お姉ちゃん今から私の下着穿いてよ。」
「はっ…?何で、それに入るわけ…」
「出来ないの?」
じっ…と見つめてくる沙希。
天使の顔に悪魔の瞳が揺らめいた。
渡されて、1分程戸惑った後に意を決して子供らしい黄色いショーツを穿いていく。
頭一つ分体格が違う上に、二次性徴期真っ只中の佳那のカラダ。
尻が入り切らずにゴムが肉に食い込んでしまう。
次に水色のキャミソール。
一応パッドは入っているらしいが、それでもきつきつだ。
「うぅ…」
何でこんな目に、と思いながら鏡を見る。
例えるならば、無理をしている大人と言うのが正しい印象だろうか。
それでも、腹の奥底がズクンと疼く感覚に嫌気がさした。
沙希の方は先ほど着ていた服をもう一度着たらしい。
スンスンと香りを嗅いでいる姿はまさに変態そのものだった。
二人はリビングのエアコンを着ると、沙希の部屋に移動した。
佳那をベッドに座らせて沙希の方は自分の勉強机の方に座る。
沈黙。
フンフンと沙希は部屋の中をしげしげと見渡していたが、佳那の方は何も口に出すことが出来ない。
どうすればいいのか、時計の針の音だけが響いていた。
「ふふ、見てお姉ちゃん。私ね、頑張って夏休みの宿題の絵日記を描いていたんだ。」
おもむろに立ち上がり、机の上に置いてある冊子を見せてくる。
年相応の笑みを浮かべながら、見せびらかすように。
パラパラとめくり、或る1ページを開いた。
「これ、この間ね、『私がお姉ちゃんに入る前』にお姉ちゃんと行った夏祭りのページ。楽しかったなぁ、お母さんに浴衣を着付けて貰って綿あめ食べたり、かき氷を食べながら花火を見たり…」
丁寧に二人が着ている着物の柄まで色鮮やかに描かれており、夜空に浮かぶ大きな花火は彼女の楽しかった思い出を象徴するかのよう。
見開きの隣のページとは力の入り具合が全く違う。
脳裏に、あの日の記憶が思い浮かぶ。
それすらも男の精神のフィルターがかかり、妹に欲情しぞわっと寒気を覚えた。
ビリッ
だが、彼女はウットリとした表情でそれを千切り、一枚の紙にした。
まるで価値が無い、と言わんばかりに。
表情と全く連動していない行動に、戦慄してしまう。
小さな手でグシャグシャにして、紙の玉にしていく。
あまりの所業に、彼女はワナワナと唇を震わせ、小刻みに首を振った。
「ねぇ、お姉ちゃん。これ、元通りに出来る?」
ゴミ箱に棄てる様に投げる妹。
パスッと力の抜けるような音をたてて転がる。
破かないように、丁寧に開く姉。
思わず涙が零れた。
ポタ、ポタと紙に染みを作っていく。
皺だらけになった絵日記、満面の笑みの二人の顔にグシャグシャの折り目がついている。
何とか伸ばそうとしても元の状態には戻らない。
「これと同じだよ、お姉ちゃん。」

恍惚の表情を浮かべ、腰をくねらせる妹。
再び吐き気を覚えてしまう。
乗っ取られている間の記憶がフラッシュバックしてきた。
そして否応にも股が濡れて行く。
こんな可愛い女の子(私)を乗っ取って支配していたなんて、と。
「いくらお姉ちゃんが憑依されていたことを、こんなに気持ちいい、素敵な事を否定したって…」
甘ったるい声が耳に響く。
自分のやってきた事がどんどん溢れ出していき、唇が歪む。
卒業式の静かな場所で、ふと思い出し笑いをし掛けて堪えるような…
やってはいけない、と押さえつけるが故に溢れ出してくる欲望。
「やだ、やめて、この子の顔で、声で言わないで…」
そう、本心では認めているのだ。
興奮していると。
大切な、優しい妹が乗っ取られて、私を詰っているこの瞬間に。
「お姉ちゃんの細胞一つ一つに、脳ミソの皺の一つ一つに、刻まれちゃってるんだよ?」
穢れを知らなかった私が、染め上げられていく感覚に、倒錯しているのだ。
変えられていく、変わっていく恐怖も本物。
だが、変えていくこの背徳感もまた、本物。
「あ…ぁ…」
声が震える。
頭の奥底の声に抗えなくなっていく。
「興奮してるでしょ?妹が下種な男に乗っ取られて、大切な思い出をグシャグシャにされている事に。」
「やだ…やめて…やめ…」
それでも、私は坂口佳那として、今までの私を保とうと否定する。
否定しないと、自分は自分で居られなくなる。
「この絵日記と同じなんだよ、刻まれた皺は伸ばしても、元通りには絶対にならないの。」
「そん…な…んっ…やっ…」
ゾクッとした。
そう、もう戻らない、戻れないのだ。
この紙も、私も。
「ほらまた気持ちよくなっちゃったんでしょ?この状況に。」
「ちがう…」
ずくん、とまた子宮が疼いた。
否定しても私のカラダは肯定させられて、いや、している……
「知ってるんだよ、私に移動した後、脱衣所でお姉ちゃんが私のカラダをチラチラ見てたの」
「ちがう…!」
意識せずにそうなっていた。
もう私は、本当に、変えられてしまったのか。
「さっき、おまんこも流していたのに私の下着を穿いて濡らしてるんでしょ?知ってるんだよ。」
「ッッ…!」
言い当てられる、意識が股間に行って、クチッと粘着質な液体が溢れているのを感じた。
それだけで更にあふれ出てくる。
「ほら、きちんと拭いたのに、私のショーツがグッショグショ…さっき私が入って居た時より濡れてるんじゃないかな?」
「それは貴女のせいで…!」
でも否定しなくちゃいけない。
佳那は必死だった、怒りをこみあげさせ無理やりにでも支えようとする。
精神は倒壊寸前の家屋のようなのに。
「でも、今のお姉ちゃんはそうでしょう?」
「こんなの私じゃない!」
頭を抱えて耳を塞ぎうずくまる。
外から自分を守るように。
でもそのベッドの上で、妹の匂いが鼻腔をくすぐった。
それすらも嫌気がさす。
「…そうだね、お姉ちゃんは『変えられちゃった』んだから」
「やめてっ!」
変わりたくない、元に戻りたい、と。
悲嘆する佳那。
「興奮するでしょ…?このカラダがどんどん染め上げられていくの。」
ゆっくりと近づいてくる沙希。
耳打ちをするように、ぼそっと告げた。
「そんなことない…」
涙があふれ、鼻声になる。
頭が痛くなってくる。
心拍数が上がって、何もかもがぐちゃぐちゃになってきた。
「分かるんだよ、おまんこ辛いよね?苦しいよね?自分に正直になりたいって…」
甘い甘い誘惑する声。
歪められたとはいえ、愛おしい人からその言葉を告げられて正気でいられるのだろうか。
「ぅ…ぁ…」
うめき声を上げる佳那。
頭の中ではミキサーのように意識が混ざり合おうとしていた。
その様子を見た沙希は救いの女神のように声をかける。
「大丈夫、私も、すぐお姉ちゃんと同じになるから。」
「同じ…?」
バッと顔を上げる佳那。
沙希は目を合わせて微笑む。
「染め上げたらいいの、お姉ちゃんの好きなように…」
「そめ、あげる…」
ゆっくりとTシャツを脱いでいく沙希。
ストリップのように見せつけて行く。
幼いカラダだが、陰毛が少しずつ生えていこうとしている股間。
小さいが膨らみが現れている胸。
先ほどあれだけ夢想した肢体を好きにしていいと、投げ出されているのだ。
「犯したいでしょ、心のおちんちんが、このカラダを滅茶苦茶にしたいって」
頬を染めて上目づかいで誘惑する沙希。
ショーツも全て脱いで、ベッドの上に乗って壁に凭れ掛け、大股を開く。
おちんちん、という言葉に強く反応する佳那。
「したい、したい…」
闇夜で光に誘われる虫のようにフラフラと近づく佳那。
その目には正気の光は無い。
「ヴぉぇっ…」
喉を膨らませ、口から透明な棒を吐き出す沙希。
それは双頭ディルド―と呼ばれるモノ。
佳那も全く知らないソレだが、使い方は全て分かってしまっていた。
差し出される、唾液まみれのディルドを受け取った佳那は、ショーツをずらして自分のナカに突っ込んだ。
「あっ…んっ♪」
ズチッグチュッと水の音を立てて中に咥えこむ。
子宮口が先端に吸い付いて固定された。
ぶらぶらする感覚に既視感を覚える佳那。
ニヤリと嗤うと、沙希へと襲い掛かった。
「きゃっ!」
ズチュッと重い音がして、沙希のナカにもディルドが突っ込まれた。
小さな膣を広げ、子宮を押し上げる。
ハァハァ、と舌を突き出して涎を垂らす佳那は最早獣のようであった。
「沙希、沙希、沙希、沙希、沙希、沙希……!!!」
狂ったように妹を求める佳那。
ぷるんぷるんと胸を揺らしながら、沙希の唇に吸い付く。
舌を突っ込み、その全てを喰らい尽くすように。
「んっ…ぁん!おねえちゃ、はげし…!」
パンッパンッ!と強く腰を打ち付ける佳那。
童貞のセックスのような様相だ。
ある意味、正しく交尾をしていると言っても過言ではない。
「沙希!気持ちいい!?もっと、もっと染めてあげる…!」
唾を吐きながら迫る。
最愛の妹を滅茶苦茶にすることが至上の快楽、と言わんばかりの形相。
「らめ、おねえちゃん!わたし、んぁっ、んぁあ!」
沙希の方は、体格の大きい彼女にのしかかられ、抵抗することが出来ていない。
幼い快楽をジュプジュプと享受するのみだ。
「うへっ…いい顔、してるわね…わた…お、おれも興奮して、やば…染まるぅ♪」
口調が徐々に男のモノが混ざり始めてくる佳那。
もう既に境界線は無くなりつつあった。
純白の白い布が黒く染め上げられるのではない、布の材質ごと変わっていくような感覚。
「おねぇちゃん染め上げられてる…やば、きもち…いぃよぉ♪」
沙希の方もその姿を見て興奮していた。
あれだけ嫌がっていた少女がここまで墜ちるなんて。
膣内が締まり、快楽が噴出する。
「イく!沙希、イっちまうぅ!」
「んぁぁっ!イっちゃう、ぜんぶ、ぜんぶまざるぅううう!」
「「イくぅううううううう!!!」」
互いに互いの身体を抱き寄せながら絶頂する二人。
ベッドを軋ませ、痙攣する姿は一つの美術品のようだ。
喉が渇いた時に飲むスポーツドリンクのように、全身にすぅっと冷感が行きわたっていく。
淫臭が漂う部屋に、ただセミの声が響いていた。
「はぁ、はぁ…」
「んっ…あっ…染め上げられちまった…へへっ、沙希ぃ…もう、『私』戻れなくなっちゃったよぉ…」
にへらっと嗤う佳那。
今日何度目かの涙を流してしまう。
だが、これが最後になるだろう、と二人は予感していた。
「えへへっ、よかった、お姉ちゃんくしゃくしゃになっちゃったね…♪」
汗で髪の毛がベタベタになっている二人。
笑いあってお互いの素肌をペタペタとくっつけ合う。
「えへへ…凄い、私なのに私じゃない…こうやって演じてる気分もあるのに…不思議な気分、でもとても、とてもスッキリして…」
感慨深く語る佳那。
まるでテレビ通販のCMを見て居るような気分だ。
「生まれ変わった気分でしょ?」
「うん、とっても幸せ…さっきまで自分が抵抗していたのがバカみたい!」
ある意味前の侮蔑ともとれる言葉。
嫌味の成分はひとつも含まれていないのだが、それほどまでに彼女は清々しい気分になっていた。
もう完全に染まりきったな、と沙希はニヤニヤしながら考える。
「ねぇ、お姉ちゃん、自由研究がね、まだ残っているんだけど…」
そう言えば、と思い出したように沙希は言い出した。
風呂に入ってから見てくれる約束だったよね?と目を向ける。
「もー、私はもう沙希に染め上げられちゃったんだから、やりたい事分かってるよ?」
忘れていないよ、と告げる佳那。
だがもう、彼女達はそれについて解決してしまっているようだった。
「うん!お姉ちゃんの学校、みんなみーんな染め上げてレポートにしちゃおう!」
ゴポッと水の音を立てる沙希。
瞳孔が開き、年不相応の笑みを浮かべる。
佳那はそれに対して身震いをしてキスをした。
「でもその前に、もう一度お風呂に入ろう!二回戦、だよ♪」
二人は着替えを取ってまた一階に降りて行く。
今度はお姉ちゃんの服が着たい!と言う沙希の声が微笑ましい。
太陽は傾き、部屋には西日が差し込んでいる。
カナカナと鳴くヒグラシの声が、遠く遠く山に響き渡り続けた。
【キャラ設定絵】